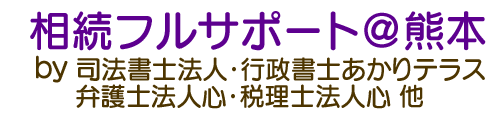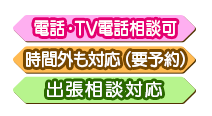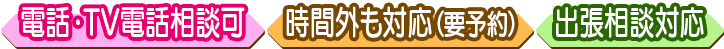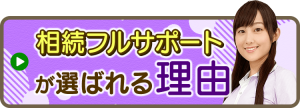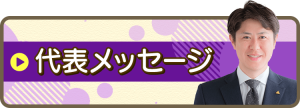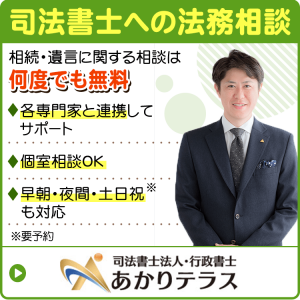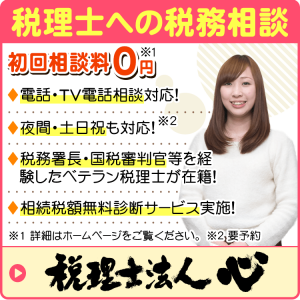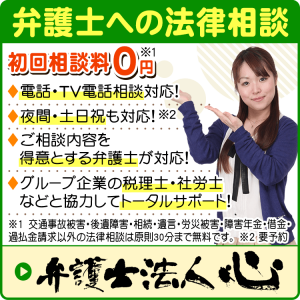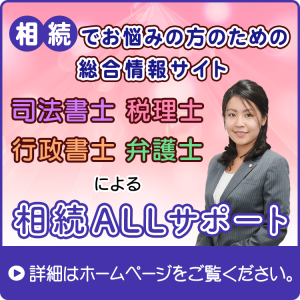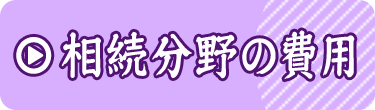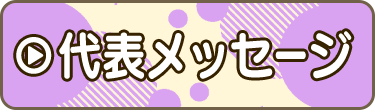東区で相続をお考えの方へ


1 東区の方の相続相談
相続で誰にどのような財産を残したいのかを検討したり、相続人が困らないように生前に対策できることを考えたりする際は、まずは法的な観点から適切な内容となっているのかを確認することが大切です。
相続をお考えの東区の方は、まずはお気軽にご相談ください。
相続について原則無料でご相談を承っております。
2 相続発生後のご相談も承ります
⑴ 各種調査について
遺言が残されていない場合は、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。
そのため、まずは法定相続人が誰なのかを確定させる調査や、相続財産の調査が必要になってきます。
戸籍を取り寄せたり、金融機関に問合せをしたり、不動産の有無を確認したりと、やらなければいけないことが多数生じます。
こういった手続きを専門家に任せることで、ご自身の負担を大きく軽減させることができます。
相続開始後の必要な調査について、ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
⑵ 各種手続きについて
いざ相続手続きをやろうと思っても、時間がなくて思い通りに進まなかったり、手続きが難しくて行き詰まってしまったりと、なかなか計画通りには進まないものです。
遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の払戻しなど、相続に関する手続きは多岐に渡りますので、適切な手続きをスムーズに進めるためにも、専門家にご相談ください。
3 相続を適切に行うために
生前対策がきちんと効力のある対策になっているかどうかを判断するためには、法律の知識が欠かせません。
遺留分を考慮した遺言の作成や、特別受益や寄与分について正確な考え方を知っておくためにも、法律の知識が求められます。
知識やノウハウがないまま相続を行った結果、トラブルが発生してしまったということのないように、相続にまつわる制度や特例をしっかりと把握することが大切です。
さらに、それらを適切に活用できるかどうかによって、結果が変わってくることもありますので、相続を適切に行えるように、相続に詳しい専門家にご相談ください。
相続の際に必要となる手続き
1 財産の名義変更

ご家族などが亡くなって財産を相続した場合でも、財産の名義が亡くなった方から相続人の方へと自動的に変わるわけではありません。
財産を相続した際には、名義を変更するための手続きが必要になります。
⑴ 不動産
相続によって土地や建物などの不動産を取得した場合、法務局で相続登記を行うことで、所有者の名義を変更します。
必要書類などについてはケースバイケースで異なりますので、司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、手続きをしないまま放置してしまうと過料を科せられるおそれもあるため、しっかりと対応することが大切です。
⑵ 預貯金・有価証券
預金や貯金、債権や株式を相続した場合には、亡くなった方の口座を解約したり、名義を亡くなった方から相続人の方へと変更したりする必要があります。
手続きの方法は金融機関によって異なる場合がありますので、これもあらかじめ司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
⑶ その他の遺産
他にも、自動車や保険契約を受け継ぐ場合や、亡くなった方が経営していた会社の後を継ぐ場合などにも、様々な手続きが必要となることがあります。
2 相続放棄
遺産の中に多額の借金が含まれる場合や、遺産を相続したくない場合には、相続放棄の手続きが必要となります。
相続放棄の手続きを行うに際しては、遺産を処分したり隠したりしてはいけない、期限内に家庭裁判所での手続きをしなければならないなどの注意点があるため、お早めに専門家にご相談ください。
3 相続税の申告・納付
遺産の価額が基礎控除の範囲を超えると、相続税の申告・納付が必要となることがあります。
相続税の申告・納付には期限があるほか、特例や控除の制度を利用するか否かによって納付すべき税金の額が変わるケースもあります。
相続税については、まず税理士に相談されることをおすすめします。

相続で困った場合の相談先
1 司法書士

相続登記で困った際には、司法書士に相談しましょう。
特に、令和6年4月1日から、相続によって取得した不動産の登記が義務化されています。
不動産の登記名義が、親や祖父母等のままであるという方は、司法書士に速やかに相談しましょう。
遺言書がある場合は、遺言書で相続登記の手続を進めることができますし、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
司法書士に依頼せずに遺産分割協議書を相続人間で作成することもできますが、法務局での登記手続ができない遺産分割協議書を作成してしまうおそれがありますので、司法書士にお任せすることをオススメします。
2 税理士
相続税がかかるかどうかご不安な方は、税理士に相談されることをオススメします。
相続税は、相続財産が「3000万円+600万円×法定相続人の人数」まではかかりません。
ですので、相続財産がこれ以下であれば、相続税申告を心配する必要はありません。
ただ、相続財産の中でも不動産は注意が必要です。
よく、固定資産税評価額を基準に、相続財産額を試算されている方もおられますが、固定資産税評価額は、あくまでも固定資産税を算出するためのものですので、相続税評価の場合は、異なる基準が用いられます。
特に、田畑や雑種地が相続財産の中に存在する場合は、注意が必要です。
場所にもよりますが、倍率地域の場合、固定資産税評価額の20倍もの価額で相続財産評価がなされることがあり、予想もしなかった相続税がかかることがあります。
ご自身の相続が相続税の対象となるか不安な方は、税理士に相談しましょう。
3 弁護士
⑴ ご生前の相続対策の場合
遺言書の作成を弁護士に相談しましょう。
遺言書の作成に加えて、任意後見契約書の作成や財産管理契約書の作成も相談しておくと、更に安心です。
⑵ ご逝去後の場合
遺産分割協議書の作成について、弁護士に相談しましょう。
特にもめていない場合ももちろん相談できます。
なお、相続人間で紛争になっている場合には、弁護士にしか依頼することができません。

相続について相談する時に準備しておくといいこと
1 資料を揃えておく

相続についてご相談いただく際には、あらかじめ資料を揃えていただくと、相談がスムーズに進めることができます。
事前にご準備いただくといい資料としては、亡くなった方や相続人の方の戸籍、亡くなった方が使っていた通帳やキャッシュカード、生命保険の証券、自宅の固定資産税評価証明書などが挙げられます。
もっとも、これらの資料が無くても相談は可能ですし、相談の中で必要な資料をピックアップしていくこともあります。
2 相続人の関係を整理しておく
相続について相談いただく際には、亡くなった方の子や親、兄弟姉妹など、他の相続人についてお話を伺うことがあります。
相続人の人数が多くなり、登場人物の数が増えると、ご相談の中で相続人の関係を整理・把握するために時間を要するおそれがあります。
そのため、あらかじめ相続人の関係を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
しかし、中には「誰が相続人になるのか分からない」というケースもあります。
こうした場合、相談の中でアドバイスを受けながら、相続人の関係を整理することができます。
3 お悩みや質問したい事項をメモしておく
相続について相談する際には、どういう点に悩んでいるのか、どのように解決したいのか、どういう結果を望んでいるのかなど、ご自身の希望や論点をある程度決めておくことが大切です。
ご自身のお悩みや質問したい事、ご自身がどうしたいのかなどについては、できればあらかじめメモしておいていただき、相談時にお見せいただくと、より的確にアドバイスさせていただくことができます。

受付時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
平日8:30~18:00
※ 時間外の相談は事前にご予約ください。
所在地
〒861-8035熊本県熊本市東区
御領2丁目28番14号 大森ビル御領203号
096-285-6841
東区で相続にお悩みの方はご相談ください
遺言を作成しても、形式面が適切でないと無効になってしまうおそれがあります。
また、内容面の検討が十分でないと、思いどおりの結果にならないことや、かえって相続トラブルの火種になってしまうこともありえます。
遺言を作成する際には、司法書士などの専門家にご相談ください。
また、相続で不動産を受け継いだとしても、財産の名義が自動的に変更されるわけではなく、相続によって所有者が変わった旨を法務局で登記しなければなりません。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されるため、今後は不動産を相続した際には早めに登記の手続きを済ませなければなりません。
ただ、不動産の登記申請について、どのような書類を揃えてどこへ提出し、どのように手続きをするのか分からないという方も少なくないかと思います。
相続登記にお悩みの方は、登記の専門家である司法書士へご相談ください。
相続財産が一定額を超えると、相続税の申告・納付が必要になります。
ただ、どのようなケースにおいて申告・納付が必要となるのか、ご自身で判断するのが難しいこともあるかと思います。
相続税にお悩みの方は、税金の専門家である税理士にご相談ください。